
型取り用のシリコンゴム一キロ3500円なり
流し込み用プラキャスト一キロ2500円なり
バリヤーコート750円なり
離型剤スプレー1050円なり
〆て7800円でした。これで上手くやれば、
小さめのものならいくつか複製することが出来ます。 他に必要だったものは
油粘土、プラ版(前に使った残りなので只)
紙コップ、割り箸(家のを使って只)
調理用秤(家のを使ったが、後で購入。500円なり)
でした。
これらは梅田のほびっとという模型店で購入しましたが
大手の模型店なら必要な資材はだいたい扱っています。

周りにはプラ板を切って、ビニールテープでつなげた
枠をはめ込み、隙間がないように粘土でふさぎます。
周りの穴は型同士を合わせたときにぴったり合わさるように
鉛筆などで開けた「ダボ穴」と呼ばれるものです。
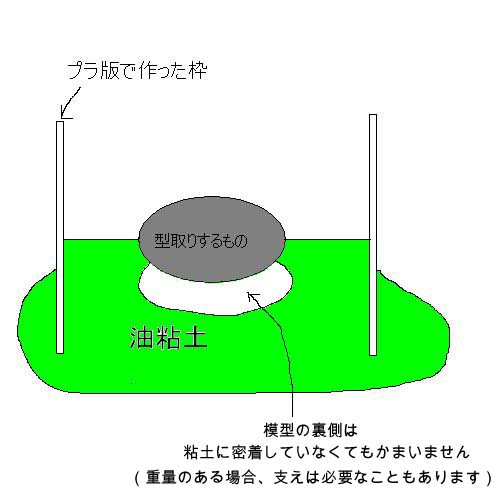
さほどきっちりした形でなくても大丈夫。
ケント紙などで作ってもいいですが、
紙などを使う時はバリヤーコートを一応塗っておきましょう
(シリコンがくっつかないように)

このように紙コップいっぱいでだいたい200グラムですね
重量にあわせた量の硬化剤を入れるのですが
なぜか規定量入れたらシリコンゴム半分(500グラム)使ったところで
硬化剤がなくなってしまいました(^-^;)
あわてて硬化剤だけ追加購入、250円なり。
硬化剤は少なめでも時間を置けばだいたい硬化しますので
大丈夫です(よく攪拌すること)
硬化には何時間もかかるので、作業時間はたっぷりあります
落ち着いてやりましょう。

さほど気泡は入らず、模型になじんで密着してくれます
しかし、念のため気泡が入らないように
こうして割り箸を使って細くたらしたゴムを
少しづつかけて、模型の表面を覆います。

このまま半日〜一日ぐらい放置してシリコンゴムが固まるのを待ちます
私はこの、片面を型取りするのに300グラムのシリコンを使用しました
とあるガレキ現役の方にお話したところ「多すぎる」んだそうです
(^-^;)慣れないうちはがっしりした大き目の型のほうが
失敗しないんですが
熟練者になると、ギリギリのわずかな量のシリコンでやられたりします
また、そういう方は全部のシリコンを新しいものでやらずに
模型の表面、一層覆うぐらいの部分を新しいシリコンでやり、
周囲のあまり重要でない部分を埋めるのには
古くなったシリコン型を刻んだものを混ぜて
量をかせいだりします。

あまりきれいにはがれませんでした(^-^;)
(第一の失敗でした) 油粘土表面にはバリヤーコートを塗っておきましょう。
一度プラ版の枠をはずしていますが、
この辺はアバウトでも大丈夫。
「ダボ穴」が最初とは逆に飛び出した状態になっていますね。
これで二つの型がずれずにぴったり合わさるのです。

シリコンの面にはバリヤーコートを塗っておきましょう
これを忘れるとシリコン同士がくっついて大変なことになります

模型が完全に隠れるように埋め込みます

この時、粘土製の原型だとシリコンゴムにくっついて
破損することがあります。
模型表面にバリヤーコートを塗っておけばある程度防げますが
模型のディテールは犠牲になるのでお勧めしません
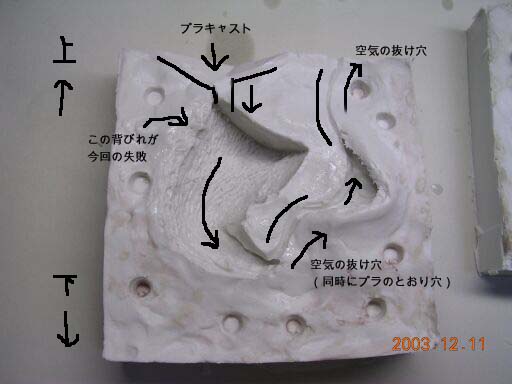
カッターナイフやデザインナイフでシリコン型を切って作りました
(最初から粘土を使って、そういう通り道ができるようにしておく
方法もあります)
これは最初に粘土に模型を埋める時にどちらを上にして、
気泡が出来にくいようにするか決めておいたほうがよいです
基本的にこういう凸凹の大きい物はシリコン型を置いた時に
凹凸がなるべく下向きになるようにしましょう
ここで失敗ですが、ゴジラの背びれが斜め上をむいており
気泡が出来る原因になってしまいました(⊃Д`)
ゴジラののど下からプラを流す形にして
逆に左に傾けた置き方のほうが良かったようです。
この場合、ゴジラの首後ろからプラを流しいれ
口先の空気穴から空気が抜けると同時に下あごのパーツに
プラが流入、下あごの反対側から空気が抜ける形になっています。
もしも単純な形で、気泡が出来ないようなものなら
空気抜きの穴はなくても良い場合もあります。

